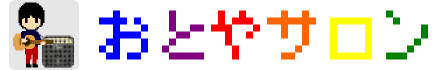きょうメルマガで紹介したオンラインベース講師のScott Devineさん。
http://www.scottsbasslessons.com/online-video-bass-lessons
無料で公開しているレッスン内容がすばらしいだけでなく、活動の仕方が最先端で、現代のミュージシャンがみならうところがたくさんある。
インターネットを活用した個人活動で、影響力をつけている。ブログで大量のレッスン動画を無料公開し、メルマガや練習用バックトラックも無料。DVD教材やレッスンスクールがバックであるが、それもとてつもないサービス量で納得。Webを活用して個人の力を最大化できることを、すべてやっている。
現代の音楽活動のひとつの極みがある。非常に参考になる。
で、おもしろいのはこの動画。ここではいったんベースをおいて、ちょっと大事な話をしようや、ていう内容。「いちばん大切なこと」というタイトル。
内容をまとめると、
「わたしはもしかしたらすごく成功しているように見えるかもしれない。
しかし、なんのことはない。ちいさなことをしてきただけなんだ。
凄腕のベーシストだって、最初は何も知らなかったんだ。ジャコ・パストリアスも、フリーも、はじめは音の出し方さえ知らなかった。スタートはみんな同じなんだ。
やってきたのは、ただちいさなことをひとつずつ身につけてきたってことだ。
なによりも大事なこと、それは、ちいさなことをくりかえしやることだ。
それはつまり、きみにだってできるということだ。
難しいことをしなくていいんだからね。まいにち、ちいさなかんたんなことをするだけだから。
目標は大きく設定してほしい。でも、やることはできるだけちいさなことにするんだ。それをまいにちかさねていくんだ。長い時間の中で、少しずつつみあがったちいさなブロックが、やがって大きくて強固な建造物をつくりあげるんだ。
まいにち、どんなちいさなことでも、その日じぶんが達成したことをほめてやるんだ。まいにち、ちいさくても、きのうよりよくなっている。それをほめたたえるんだ。
それをやってれば、だれだって失敗なんかできない。ちいさなことでいいんだ。」
というようなことを言っている。
イチロー選手がいつも言っていることと同じだが、言う人が違うと、感じ方もちがってくる。ミュージシャンだって同じということだ。
できる人には才能があるというのは、何もやらないヤツの言訳にすぎない。ジャコパスもフリーも、みな最初は何もできなかった、何も知らなかった。
目標はでかくていい。でもやることはシンプルに、ちいさいことでいい。人間は弱いから、ちいさいことしかできない。
大きな結果、すごい技にみえるのは、たまたまその日はめたちいさなピースが、大きな絵を完成させる最後のパーツであったという瞬間に遭遇したにすぎない。本人からしたら、いつものようにちいさなことをしただけ。
真理なんてそんなもんだろう。
この人のレッスン動画は短いので、毎日でもできるはず。ベースプレイヤーにはおすすめ。
英語が苦手だったら、わかるように翻訳します。ご連絡ください。