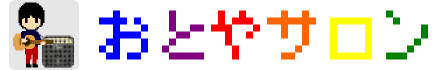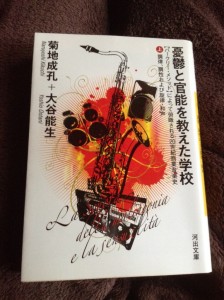第1講義では、バークリーメソッドの先祖である「十二平均律 」の成立までの歴史を超ハイスピードで見ています。
「十二平均津 」とは「ドレミファソラシド」のことです。
現代人は当たり前に素晴らしい音楽の恩恵を受けていますが、それは過去の音楽家や数学者や科学者たちが少しずつ音の仕組みを発見し、音楽の秘密を解き明かしてきたからということを意識してましょう。
日常的に聴いている音楽のほとんどは「ドレミファソラシド」の音階で作られているわけですが、そもそもこの「ドレミファソラシド」という7つ(半音を含めれば12)の音の並びが確立されるまで、数百年、数千年以上かかったのです。その間に、教会やら宗教やら権力者らの気分によって使っていい音がころころ変わったりして、多くの人が殺されたりしたのです。
その「ドレミファソラシド」のシステムである「十二平均律」、18世紀にバッハがやっと完成させたのですが、それまではずっとドレミのない世界で音楽を作るしかなかったのです。
バッハが1722年と1744年に『平均律クラヴィア曲集』 を発表してからですので、それからまだ292年くらいしか経っていないんですね。
講義は参考を音源を聴きながら進められていきます。
紹介されている音楽はYoutubeで見られるものも多いので、内容と一緒にまとめてみます。
はじめに、現代の商業音楽の主流であるバークリーメソッドによってつくられた「音韻情報過多」的な音楽の典型例からスタートします。
Michael Brecker – Don’t Try This At Home
このように調性があいまいで、転調が多くてどのキーなのかよくわからない、やたらふわふわした感じというのが、俗にいうバークリーアレンジ「バークリー症候群」などという曲のお手本のような曲です。記号的な操作を盛り込むことで「スゴイだろー」と思わせ、イコール「スゴい」音楽と思い込んで酔っている(批判しているわけではありません)、現代の商業音楽教育の到達形のような例として代表的なサウンドなのですね。
ここから一気に歴史を巻き戻り、グレゴリアン・チャント やオルガヌム という、ヨーロッパ古代のほとんど音程変化のない、声を一定の長さ重ねただけのような音楽を振り返って紹介しています。
で、すぐバッハの『平均律クラヴィア曲集』に入ります。はや(w)
VIDEO
現代のわたしたちが聴くような、ドラマティックなストーリーのあるサウンドになっています。えんえんと聴いていたいくらい、美しく緊密に計算されつくした音楽です。
ここから、世界の音楽は各地域の民族音楽しか存在しなかった(ヨーロッパのグレゴリアン・チャントもヨーロッパの民族音楽です)というハードコアな状態から、
誰もが楽しめる十二平均律というポップな世界に統一しようと動いていきます。
その「ポップ化思考」の最果てがバークリーメソッドであると言われており、十二平均律をベースに、すべての音を楽譜に表記して再生・反復・消費に堪えるような音楽としてデジタライズ化していこうという試みの結実ということです。
十二平均律というベーシックテクノロジー(基幹技術)をもとに、ダイアトニックコードはじめあらゆる作曲法が開発されていくわけですね。それはすべて十二平均律のモディフィケーション(修正版)であるのです。ビートルズもバークリーメソッドもモディフィケーションなのです。
そういったシステマティックな在り方や商業主義に飽きて、もっと自由な表現をしていいはずだという意識が露骨になってきたのが20世紀。次からはそういった流れの中で生まれた音楽の紹介になっていきます。
Atrium Musicae de Madrid-Tarentella Neapoli Tonum Phyrigium
VIDEO
これは「純正律 」という、十二平均律とは違う音の並べ方をした調律で作られた音楽です。
聴いてみると、少し音が外れているように感じるのです。しかし、純正律では正確な音高を演奏しているのです。
音が外れていると感じるのは、わたしたちの耳が生まれたころから平均律に人工的にチューニングされてしまっているからなのです。
それから、平均律がもたらした良い面と悪い面を考察して、「音韻」と「音響」の話をしてから、また歴史の流れにもどります。
平均律は1オクターブをまったく等間隔に分割します。それによってどの調に転調しても誤差が生じなくなり、どこでも自由に転調してよくなりました。この快楽が強烈なのです。だから、転調しまくってふわふわしたおしゃれ感を演出するのが流行るわけです。
しかし、じつは平均律による分割は、自然物理からは逸脱しているので、中には平均律が濁って聴こえるという人もいる。
自然物理に純粋にしたがって1オクターブを分割した調律が「純正律」です。純粋な美しい調律、という意味ですね。これの信奉者は多いです。
人類は平均律で音楽を作るのが主流の歴史を選んだわけですが、もしかしたら純正律で音楽を作るのがふつうの世界があったのかもしれないのです。それは別のパラレルワールドの話でのことですね。
「音韻」と「音響」についてですが、言葉の通りです。音韻は「楽譜に書かれた情報」のことであり、ドレミとかコードとか、人間が頭の中で作っている音の意味のことですね。言葉と同じです。
音響とは、物理的に発生する音の響きに関するあらゆることです。楽器を弾いた時のノイズとか、空間の共鳴とか、楽譜に書き表せないことです。
もちろん音楽は物理世界でつくるものですから、音韻と音響は不可分です。どちらも大事。
しかし、十二平均律以降の西洋がもたらした音楽は、あらゆる音を記号化して整理しようという、「音韻過多」になってしまいました。それに異を唱える流派が、純正律や現代音楽などをやっていこうとうするわけです。
純正律の人たちは平均律を「病的」と言います。平均律音楽のセンチメンタルでドラマティックな内容を批判するのは、文学で20世紀の初頭オスカーワイルドらが唱えたArt for Art’s Sake「芸術至上主義」への反発と似ていますね。ナチュラリズム、Art for Life’s Sakeなどと言って騒いだものです。トルストイさんなんか嫌いな芸術家を名指しで攻撃する本まで出したりして、ほぼ発狂してましたからね。
バッハの曲などは、少し音響環境が悪くても良いと思いますよね。それは音韻情報が徹底的に作りこまれているからです。たとえ音響が悪くても、良くつくられた音楽は良く聴こえる。もちろん、音響まで良い環境がそろっていればもっと最高になります。
音がちっぽけでも音韻を賢くつくっていれば人を感動させることができる。これは80年代後半-90年代の日本のゲーム音楽とも共通しますよね。あの時代の人たちは、ブザーみたいな音とノイズで合計3音しか使えないという環境でドラマを作ってました。それくらい、平均律はデジタルな情報空間に存在しているのです。
そして、バッハ以降の音楽に入っていきます。クラシック音楽の世界も、十二平均律の呪縛から自由になろうと挑戦的になっていきます。
Pierre Boulez-『主なき槌』
VIDEO
Anton Webern-『オーケストラのための変奏曲 作品30』
VIDEO
アーノルド・シェーンベルグ-『浄められた夜』
VIDEO
Claude Debbusy-『沈める寺』
VIDEO
Karlheinz Stockhauzen-『ピアノ曲XI』
VIDEO
このあたりになると、ふつうの人はもうわけがわからなくなってきますよね。でもこれもきちんとした音楽表現なのです。完全に現代音楽の世界です。
こういうちょっと怪しい音楽は、SFやエイリアン系の音楽に使えるじゃん、てことでバークリーは容赦なくメソッド化しちゃっているわけです。ブーレーズさんたちクラシック界の高尚な芸術的境地としての表現でさえ、バークリーはじめ商業音楽はスコアリング用の道具にしてしまいます。
John Cage-Sonatas and Interludes for Prepared Piano
VIDEO
最後がJohn Cage。現代音楽の代表的人物です。
完全にドレミファソラシドの調律から離れ、バークリーメソッドも十二平均律も関係ないイレギュラーなサウンドの世界になっています。
プリペアドピアノといって、ピアノの中にいろいろなガラクタ(w)をたくさん仕込んで変わったサウンドを出す、という方法です。
このような感じで、十二平均律による音楽のデジタル化ポップ化の流れから、そこから逸脱しようとする現代にいたるまでの流れを俯瞰しています。
まとめ
これだけでも膨大な量の知識が入っているのですが、一つ大事なポイントを言うならば
十二平均律による記号化・大量消費用・音韻過多音楽は、確かに292年近く世界の主流の音楽ではあったが、
それとてあくまでも商業主義音楽派のヒット量産ツールというひとつの流派でしかないのであって、絶対に守らねばならぬルールというわけではない
ということです。